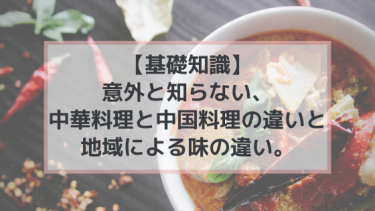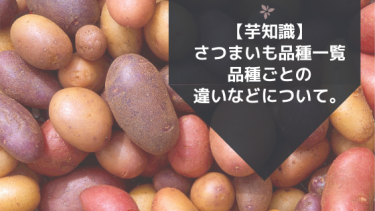そば、寿司、ラーメンと同じように日本食を代表する日本そば。ランチや行事、旅行先でも口にする方は多いと思います。そんな蕎麦ですが、暖簾やメニュー表をみて「もりそば」「十割そば」「へぎそば」など書いてありますが、実はぴんと来ない方もいるのではないでしょうか。店員さんがお店のそばのこだわりを教えてくれることもありますが、基礎知識がなくて「何が違うか正直わからない・・・」という方も多いと思います。
そして普段口にしているものが「そば」ではなく「めん」という可能性も。

そこで今回はそんな蕎麦の種類や食べ方など、そばの違いについて栄養士がご紹介していきます。これで巷のそばの違いがわかるようになり、お店も安心して入れるだけでなく、好みも見つけることが出来るようになりますよ。
そば粉の割合による種類

そば粉と小麦粉(つなぎ)の割合で呼び方が変わり、触感と香りも変わってきます。代表的なのは以下の2種類。
十割そば
「じゅうわりそば」と読み、お店によっては「とわりそば」と読むところもありますが、一般的には「じゅうわりそば」で伝わっています。そば粉100%で打っているため香り高く、コシが強いのが特徴。そば粉と水のみで打つ蕎麦は非常に切れやすく手間暇がかかり、ゆで具合の調整も難しいため、少しお高めの金額設定になっていることが多いです。
生そばとは?
二八そば
読み方は「にはちそば」。文字通り、そば粉8:小麦粉2の割合で打ったそば。つなぎ(小麦粉)を入れることで打ちやすくなり、のど越しがよくなるのが特徴。外食する際、とくに表記されていない場合、二八そばである確率が高いスタンダードなそばです。
そば粉の種類 ー挽きと篩(ふるい)ー

そば粉はそばの実を挽き、どの段階で篩にかけたそば粉なのかで色や味、香り、栄養価などが変わります。
一番粉(内層粉)
一番最初に挽いたときに出てきたものを一番粉といいます。最高級そば粉であり、別名更科粉とも呼ばれます。これはそばの実の胚乳の中のさらに中心部から出てくるもの。でんぷんが主体で見た目は白く、そば独特の触感や香りには少し欠けますが、味は甘く、のど越し良いそばになるのが特徴。一番粉でそばを打つのは非常に難しく、さらに十割蕎麦となると並みの職人では打つことが困難なことから、このそば粉を使用した十割そばは最高級蕎麦として扱われます。
二番粉(中層粉)
一番粉の後に挽き、製粉したそば粉。胚乳と胚芽の一部が主体となっていて、香りが高く甘皮も一部巻き込まれるので蕎麦らしい色をしています。一般的によく口にするのが二番粉で打ったそば。
三番粉
二番粉の後に挽き、製粉したそば粉。二番粉よりも多く甘皮が挽き込まれるので、色が濃く香り高いそばになります。歯ぬかりする(コシがない)そばになりやすいですが、柔らかいそばが好きな人にはオススメ。
四番粉
繊維質が多く、最も栄養価と香りが高いそば粉。その代わり、舌触りがぼそぼそするため、乾麺や即席めんなどとして使用されることが多いそば粉。
全層粉
一から四番粉まで篩(ふるい)にかけて分けるのではなく、すべて合わせた粉のこと。つまり外皮以外をすべて挽いたそば粉。
全粒粉(挽きぐるみ)
そばの実を外皮ごと全て挽いたそば粉。色が濃くかなりそばの香りが高いのが特徴。すべて挽くので別名「挽きぐるみ」とも呼ばれます。全層粉も「挽きぐるみ」と言われることがありますが、「全粒粉=挽きぐるみ」が正しい認識です。
そば粉の特徴を活かしたそば ー三大系統ー
【そば粉の種類ー挽きと篩ー】でも記述したように、一番粉~四番粉によって味や香りが変わります。そしてそのそば粉で打ったそばとペアリングした麺つゆの美味しさで名を馳せた【江戸の御三家】が存在します。「御三家」と言われるため、三暖簾あるわけですが、そこから御三家が代表するそばを「三大系統」とし、さらに各系統ごとに御三家ができました。
更科蕎麦
一番粉(更科粉)を使用した最高級そば。香りはやや少ないですが、色が白く、甘みがあり、歯切れやコシ、のど越しなどどれをとっても素晴らしいのが特徴的。打つのが非常に難しいそばであるため十割そば同様、価格が少しお高め。さらに更科蕎麦の十割となると非常に珍しく、並みの職人では打つのも難しいそう。御三家と呼ばれたお店は東京麻布に店舗があります。(更科そばの発祥は長野)
藪蕎麦(やぶそば)
二番粉と三番粉で打ったそばで、香り高く、そばの実の甘皮による「黄緑色」な見た目が特徴。一緒の麺つゆは辛めであるのも特徴的で、味が濃くても、負けないくらいそばの香りがします。江戸っ子の「麺つゆにちょこんと付けて、さっと食べる」風習はこの少し塩辛いそばを食べる動作が由来とされています。藪そばの名前の語源はこのそばの発祥店が竹藪に囲まれていたからだとか。
砂場
主に二番粉を使用して打ったそば。麺つゆがとにかく「甘くて濃い」のが特徴。御三家の中で一番歴史が古く、出前先でそばが少し乾いたとき、たっぷり麺つゆに浸して食べても辛くない蕎麦として流行ったそうです。その麺つゆの甘さと濃さは出前してる最中こぼしてしまうとベタついて仕方ないというほど。名前の由来は砂場と言われる資材置き場があり、そこで働き人が気軽に食べられるようにと近くで開店したためと言われています。江戸時代に存在していた砂場が南千住で現在も営業しており、文化財にも登録されています。
そば粉の特徴を活かしたそば ー他ー

ここでは三大系統以外に特定のそば粉を用いたそばについてご紹介。
田舎そば(挽きぐるみそば)
主に挽きぐるみを使用するそば。そのため色が非常に濃く、香りも高いのが特徴。食べ方としては麺つゆはあまり付けずにそば本来の味を楽しみます。見た目が黒く、どっしりしていて、食べ応えもあるため「田舎そば=十割」という誤認識が多いですが、田舎そばには二八そばもあります。つなぎに山芋など使用することがありますが、その場合、「小麦が入っていないから十割だ」というお店もたまにあるので惑わされないようにしましょう。
「このお店、色が薄いのに田舎そばって書いてある!」ということもありますが、そばの実の種類によって皮の色も違うため出る色ももちろん変わります。
正直、「江戸の白いそばに対し、地方のそばは黒いから田舎そば」と呼ばれるなど、「白いから江戸、黒いから田舎」とざっくり分けることもあり、使用するそば粉は明確ではないという考え方もあります。
変わりそば

基本的にそばは「そば粉+水(+小麦粉)」で打ちますが、それ以外に混ぜ合わせて打つそばのことを「変わりそば」と言います。
「茶そば」はそば粉に抹茶を混ぜたり、他にもからし、柚子、山椒、シソなど様々。季節を楽しむそばとして提供されることが多いです。
そばの実
そばの実によっても触感や香り、色なども変わってきます。ここでは代表的なそばの実から打つそばをご紹介します。
キタワセ
北海道で一番多く生産されるそばの実で、全国にも流通しています。外皮がきれいな黒のため田舎そばにする際、多く使用されます。
信濃一号
一番スタンダードなそばの実で、お米で例えるなら「コシヒカリ」の立ち位置にいます。扱いやすく、品質も素晴らしいそばの実とされています。
韃靼(だったん)
実は海外(中国や韓国、モンゴルなど)で栽培されるそばの実。健康ブームで一気に日本での知名度を上げた韃靼そばは、苦味が強く、「苦そば」とも言われます。苦味と引き換えに栄養価が非常に高く、抗酸化作用のある成分ルチン(高血圧予防やアンチエイジング)が通常の120倍以上といわれています。好き嫌いが少し分かれますが、健康に良いそば。このそばを食べる際はそば湯も必ず飲みたいところ。
ご当地そば

へぎそば
新潟発祥のそば。「へぎ」と言われる四角い器に、一口サイズに小分けしてそばが並べられていて、見た目もキレイなそば。つなぎは布海苔を使用し、つるっとした触感と十割そばに引けをとらぬコシが特徴。
富倉そば
長野県発祥のそば。別名「まぼろしのそば」とも呼ばれていて、つなぎにヤマゴボウを使用、十割そばに引けをとらぬコシ、そばの実とゴボウの味の相性、ヤマゴボウをつなぎとして打つことが非常に難しく、山奥の交通便の悪い地域にある希少性からその名前が付けられました。
日本三大そば
日本の三大そばについて、その土地に訪れた際は必ず口にしたいそばをご紹介します。
出雲そば
島根県、出雲のそばで出雲大社の近くなど、観光地で見ないことはないそば。種類は2種類あります。
割子そば
三段の漆器に入れて提供されるそば。見た目はお弁当箱みたいで可愛らしいです。特徴的なのはそばの入っている器に麺つゆを入れて食べるというスタイル。三段あるため薬味を変えて上から順に食べていきます。
釜揚げそば
ゆで上げたそばを水洗いせずに、麺つゆをそば湯で割って一緒に食べるそば。美味しい蕎麦だと、汁まで美味しくなる一品。
わんこそば
戸隠そば(とがくしそば)
長野県のそばで挽きぐるみを使用しているのが特徴。その他、「ぼっち盛り」と言われる一口サイズのそばの束(へぎそばに似ている)が円形のざるに5束盛られます。束は戸隠神社が5社あることが由来ではないかと言われ、神社の法師が一人で修業に耐え抜くことから「法師(ぼっち)」「一人(ぼっち)」とかけているのではないかとされています。
季節の特徴が出るそば

新そば
秋に収穫されたそばの実で打ったそばのこと。香りが高く、味が濃くなるため、そばの旬とも言えます。別名「秋新」とも呼ばれます。
ひねそば
新そばの逆であり、旬でない時期に収穫されたそばの実で打ったそば。とくに夏は旬の時期とずれていることから、そのそばを「夏新」と呼んだりします。昔は冷蔵や保管技術が優れていなかったため、香りが落ち、そば粉もまとまらず、つなぎを多く使う傾向にあったためこの名前がつけられましたが、現代では技術が発展し、季節間による品質の差はなくなってきています。
寒さらしそば
真冬の冷たい清流に浸し、寒風で乾燥させたそばの実を挽いて打ったそば。最近では寒さらしそばは「GABA(ストレスの軽減)」含有量が増加するという研究結果があります。
そば粉の企画による種類
生めん
麺に含まれるそば粉が30%以上含まれないものは「そば」と表記してはいけないという決まりがあります。
| そば | 大麦そば | 大麦めん | めん |
| そば粉30%以上 +小麦70%以下 |
小麦粉40%以下 +大麦、そば粉30%以上 |
小麦粉70%以下 +そば粉30%以下 +大麦、30%以上 |
小麦粉と合計で85%以下 |
スーパーなどで見た目はそばでも「太めん」なんて書かれている場合、それはそば粉の含有量が限りなく少ないものです。飲食店の場合は生めんであることほとんどです。
乾めん
乾めんは生めんとは違い、そば粉が30%以上でなくても「そば」と表記できます。その場合は製品表示を見て何が含まれているか見ましょう。
即席めん
いわゆるインスタントそば。こちらも生めん同様、そば粉が30%以上使用されていない場合「そば」と表記できません。
そばの食べ方による種類

もり/ざる/せいろそば
茹でた後にぬめりをとるために冷やしながら洗い、ざる、もしくはせいろに入れて提供するそば。そば猪口と呼ばれる麺つゆが入った別の容器にちょこんと付けながら食べます。麺つゆは冷汁(辛汁)がスタンダード。たまに「もりそば」「ざるそば」と2種類用意されているお店があり、「ざるそばはもりそばに刻みのりがかかっている」というところがあるので、メニュー表に2種類書いてある場合は店員さんに聞いてみましょう。
かけそば/温そば
ゆで上げたそばを水で洗った後、丼にそのそばと温かい麺つゆ(甘汁)を一緒にして提供するそばのこと。「どんぶりそば」とも言われることもあります。
南蛮そばとは?
南蛮そばとは唐辛子やねぎの入ったかけそばのことを指します。よく「鴨せいろ」「鴨南蛮」とありますが、鴨せいろはそば猪口に鴨、鴨南蛮は鴨と唐辛子、ねぎの入ったかけそばのことを言います。他にも鶏南蛮などありますが、鶏南蛮は「かわしそば」と呼ぶこともあります。
ぶっかけそば
平皿で少量の麺つゆにそばが浸り、具材などが盛り付けられているそば。
最後に
どうでしたか?これでどんなそば屋に入っても怖くないですし、そば屋巡りも面白くなるかも。さらに、自分の好みを見つけて、探求してみてください。
以上、そばの種類や食べ方についてでした。